ニュースとか色々
気まぐれへっどらいん
このヘッドラインはNEWs保存道場が気まぐれでお勧めブログを紹介してます。
マーノ・デ・サント(神の手)と呼ばれた男
472 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2008/02/24(日) 03:14:11 ID:setrRor1
ちょっと長くて申しわけないんですが、マイナーな偉人の話です。
花井貫一(1885~1939)本名・松井良次郎。富山県富山市出身。
1920~30年代、卓越したテクニックを生かした南米のサッカーが、ヨーロッパを震撼させていた。
花井は24~39年、アルゼンチンの名門ボカ・ジュニアーズでトレーナーとして活躍。
『マーノ・デ・サント(神の手)』と呼ばれ、選手から絶大な信頼を寄せられた男だった。
花井は医者を志していたが、父が日露戦争で死去。生き方を変えるため、20歳のころ欧州へ渡る。
柔術の経験があったので、大道芸のように格闘技を教え歩いた。
このとき解剖学的知識を深め、骨つぎのような治療を行っていたことが、後に人生を変える。
25歳ごろ、体育教師として客船に乗り込み、そのまま南米に渡った。
ブエノスアイレスに着いたとき、「何かが呼んでいるような気がした」という。
アルゼンチン女性と結婚し、ウルグアイ、パラグアイなどを放浪、柔術を教えてまわった。
30代なかばで、ブエノスアイレスの鉄道会社に職を得、アルゼンチンに戻ってきた。
地元のクラブの試合を観戦中、ケガをした選手への手当てがきっかけで、クラブトレーナーに抜擢。
その腕前が評判を呼び、ボカのトレーナーに引き抜かれ、アルゼンチン代表の担当にまで昇格することとなる。
ちょっと長くて申しわけないんですが、マイナーな偉人の話です。
花井貫一(1885~1939)本名・松井良次郎。富山県富山市出身。
1920~30年代、卓越したテクニックを生かした南米のサッカーが、ヨーロッパを震撼させていた。
花井は24~39年、アルゼンチンの名門ボカ・ジュニアーズでトレーナーとして活躍。
『マーノ・デ・サント(神の手)』と呼ばれ、選手から絶大な信頼を寄せられた男だった。
花井は医者を志していたが、父が日露戦争で死去。生き方を変えるため、20歳のころ欧州へ渡る。
柔術の経験があったので、大道芸のように格闘技を教え歩いた。
このとき解剖学的知識を深め、骨つぎのような治療を行っていたことが、後に人生を変える。
25歳ごろ、体育教師として客船に乗り込み、そのまま南米に渡った。
ブエノスアイレスに着いたとき、「何かが呼んでいるような気がした」という。
アルゼンチン女性と結婚し、ウルグアイ、パラグアイなどを放浪、柔術を教えてまわった。
30代なかばで、ブエノスアイレスの鉄道会社に職を得、アルゼンチンに戻ってきた。
地元のクラブの試合を観戦中、ケガをした選手への手当てがきっかけで、クラブトレーナーに抜擢。
その腕前が評判を呼び、ボカのトレーナーに引き抜かれ、アルゼンチン代表の担当にまで昇格することとなる。
473 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2008/02/24(日) 03:17:00 ID:setrRor1
当時のアルゼンチンサッカーは、プロへ向かう過渡期にあたり、熱狂的な盛り上がりを見せていた。
人気が出れば試合数が増える。試合はおのずと激しくなり、負傷者が続出する。
ところが、選手をとりまく医学レベルは、当時ものすごく低かった。
半月板の存在すら知られていなかったので、膝を痛め、若くして引退する選手が後を絶たなかった。
花井は解剖学、柔術などの経験から、運動医学の基礎を築き、その知識を元に治療に当たった。
それは、南米のサッカー選手にとっては「マジック」だった。
ビセンテ・カセレスという選手が、試合中に足の骨にヒビが入る重傷を負った。
チームメイトたちは、とてもプレーが続行できる状況ではないと思った。
しかし花井は、バッグから一本の布テープを取り出し、それをカセレスの足に巻き始めたのだ。
カセレスは試合終了まで動き回り、その後の治療も非常に短期間で済んだのである。
テーピングだけではない。試合前後のマッサージで、選手のパフォーマンスを格段に上昇させることができた。
選手の肉体管理が、より高度なプレーを可能にし、南米サッカー全体のレベルを引き上げていく。
トレーナーの重要性を認識させ、先駆者的存在となったのが、他ならぬ日本人の花井なのである。
474 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2008/02/24(日) 03:18:09 ID:setrRor1
ブエノスアイレスに開いていた診療所には、スポーツ選手のみならず、南米中からありとあらゆる患者が訪れた。
花井は誰でも分け隔てなく診た。貧しい人から治療代を貰わないこともたびたびだったらしい。
ボカのトレーナーであるにもかかわらず、ライバルチームのリーベルや、ラシンの選手を治療し、復帰したばかりのその選手にゴールを決められ、ボカが負けてしまうこともあった。
「カンイチに膝を治してもらわなかったら、とっくに引退して、故郷へ帰っていたよ」
と、リーベルの名選手、ベルナベ・フェレイラは言う。
「リーベルの選手の治療には、手を抜いてくれてもよかったのに」
ボカのフランシスコ・バラージョは笑う。
不倶戴天の仇敵同士が、互いに仲良く、花井の診療所に通っていたのだった。
花井の価値を認め、誰よりも感謝していたのは、他ならぬ選手たちだった。
監督でも、コーチでも、クラブの会長でもない。トレーナーである花井に、全幅の信頼を寄せていたのだ。
選手たちは、ユニフォームや優勝メダルを、こぞって花井にプレゼントし始めた。
試合前に集合写真を撮るときには、必ず花井を呼び、肩を組んで一緒にうつることを要請した。
「すべての試合にカンイチを帯同させてほしい。彼がいなければ、我々は試合ができない」
1925年、ボカは欧州遠征を企てたが、ビザの関係で花井が同行できないとわかると、計画の中止を求める声がわきあがったという。
475 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2008/02/24(日) 03:21:02 ID:setrRor1
前述のバラージョは、花井の親友の一人である。
第一回ワールドカップ大会、決勝を戦ったウルグアイ・アルゼンチン両チームのうち、唯一の生存者だ。
1994年に、国際サッカー連盟より特別表彰を受けたとき、彼は記者の大住良之にこう話した。
「お前はハポネス(日本人)か。おれの現役時代、最大の恩人だったのがハポネスなんだ」
1939年、花井は胃がんにより、54歳で不帰の客となった。
バラージョに棺桶を担いでくれと頼み、数日後、眠るように亡くなったという。
花井が生きた時代から、もう100年近くが経過している。
彼ははたして、日本サッカーが急速に実力をつけ、ワールドカップを開けるまでに成長することを、想像できただろうか。
【参考】
・「花井貫一という男がいた」『季刊サッカー批評』No.11(双葉社)
・北日本新聞バックナンバー
ttp://www.kitanippon.co.jp/backno/200604/05backno.html
・松井豊『マーノ・デ・サントの帰郷 アルゼンチンサッカーに生きたある日本人の物語』(文芸書房)
※花井貫一を描いた小説。
(引用者注:小説の作者は「松井豊」ではなく「晩豊彦」)
当時のアルゼンチンサッカーは、プロへ向かう過渡期にあたり、熱狂的な盛り上がりを見せていた。
人気が出れば試合数が増える。試合はおのずと激しくなり、負傷者が続出する。
ところが、選手をとりまく医学レベルは、当時ものすごく低かった。
半月板の存在すら知られていなかったので、膝を痛め、若くして引退する選手が後を絶たなかった。
花井は解剖学、柔術などの経験から、運動医学の基礎を築き、その知識を元に治療に当たった。
それは、南米のサッカー選手にとっては「マジック」だった。
ビセンテ・カセレスという選手が、試合中に足の骨にヒビが入る重傷を負った。
チームメイトたちは、とてもプレーが続行できる状況ではないと思った。
しかし花井は、バッグから一本の布テープを取り出し、それをカセレスの足に巻き始めたのだ。
カセレスは試合終了まで動き回り、その後の治療も非常に短期間で済んだのである。
テーピングだけではない。試合前後のマッサージで、選手のパフォーマンスを格段に上昇させることができた。
選手の肉体管理が、より高度なプレーを可能にし、南米サッカー全体のレベルを引き上げていく。
トレーナーの重要性を認識させ、先駆者的存在となったのが、他ならぬ日本人の花井なのである。
474 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2008/02/24(日) 03:18:09 ID:setrRor1
ブエノスアイレスに開いていた診療所には、スポーツ選手のみならず、南米中からありとあらゆる患者が訪れた。
花井は誰でも分け隔てなく診た。貧しい人から治療代を貰わないこともたびたびだったらしい。
ボカのトレーナーであるにもかかわらず、ライバルチームのリーベルや、ラシンの選手を治療し、復帰したばかりのその選手にゴールを決められ、ボカが負けてしまうこともあった。
「カンイチに膝を治してもらわなかったら、とっくに引退して、故郷へ帰っていたよ」
と、リーベルの名選手、ベルナベ・フェレイラは言う。
「リーベルの選手の治療には、手を抜いてくれてもよかったのに」
ボカのフランシスコ・バラージョは笑う。
不倶戴天の仇敵同士が、互いに仲良く、花井の診療所に通っていたのだった。
花井の価値を認め、誰よりも感謝していたのは、他ならぬ選手たちだった。
監督でも、コーチでも、クラブの会長でもない。トレーナーである花井に、全幅の信頼を寄せていたのだ。
選手たちは、ユニフォームや優勝メダルを、こぞって花井にプレゼントし始めた。
試合前に集合写真を撮るときには、必ず花井を呼び、肩を組んで一緒にうつることを要請した。
「すべての試合にカンイチを帯同させてほしい。彼がいなければ、我々は試合ができない」
1925年、ボカは欧州遠征を企てたが、ビザの関係で花井が同行できないとわかると、計画の中止を求める声がわきあがったという。
475 :おさかなくわえた名無しさん[sage]:2008/02/24(日) 03:21:02 ID:setrRor1
前述のバラージョは、花井の親友の一人である。
第一回ワールドカップ大会、決勝を戦ったウルグアイ・アルゼンチン両チームのうち、唯一の生存者だ。
1994年に、国際サッカー連盟より特別表彰を受けたとき、彼は記者の大住良之にこう話した。
「お前はハポネス(日本人)か。おれの現役時代、最大の恩人だったのがハポネスなんだ」
1939年、花井は胃がんにより、54歳で不帰の客となった。
バラージョに棺桶を担いでくれと頼み、数日後、眠るように亡くなったという。
花井が生きた時代から、もう100年近くが経過している。
彼ははたして、日本サッカーが急速に実力をつけ、ワールドカップを開けるまでに成長することを、想像できただろうか。
【参考】
・「花井貫一という男がいた」『季刊サッカー批評』No.11(双葉社)
・北日本新聞バックナンバー
ttp://www.kitanippon.co.jp/backno/200604/05backno.html
・松井豊『マーノ・デ・サントの帰郷 アルゼンチンサッカーに生きたある日本人の物語』(文芸書房)
※花井貫一を描いた小説。
(引用者注:小説の作者は「松井豊」ではなく「晩豊彦」)






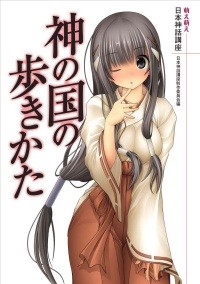

紹介したくてたまらんのだろうが
「神の手」じゃなくて「聖者の手」だと思うが…
ありがとう
南米サッカーが強いのは、
昔の日本人が当時の選手を、
ボカボカ治療したからだ。
構ってちゃんは仕方ないなぁ~。
えっ?